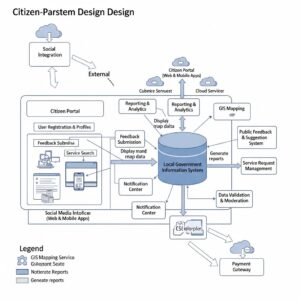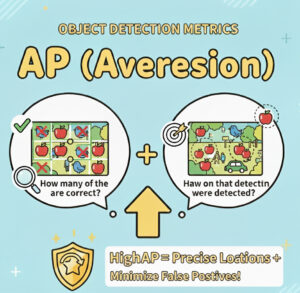360°×AI 実務導入チェックリストと「海中構造の知覚」システム設計

360°×AI 実務導入ガイド(やさしく解説)
このページは、海の中の構造や状況を、360°動画や静止画+AIで 「実体験に近い形」で理解できるようにするための入門ガイドです。 まずは既存の360°YouTube動画(例: 海中の360°動画 )を埋め込み、時間に合わせて説明を表示するだけでも効果があります。 その後、必要に応じて「自社ホスティング(Pannellum/A-Frame)」や「AIによる自動注釈」へ段階的に移行します。
※専門用語は最小限にし、なるべく平易な説明でまとめています。現場で使える「手順」と「注意点」を中心に構成しています。
0. 全体像(やることの流れ)
① 画像や動画を用意(撮影/収集)
- カメラ:Insta360 / GoPro MAX / RICOH Theta など
- 水中対策:ライト(明るさ高め)、距離の目安(レーザー目盛など)
- まずは既存素材:YouTubeの360°動画や静止画を活用
② 前処理(つなぐ・揺れを抑える)
- ステッチ:メーカー純正ソフトなどでOK
- 出力形式:横長の球面画像(Equirectangular/2:1)推奨
- 手ブレ抑制:Gyroflow 等で安定化
③ 見やすく補正+AIでポイント抽出
- 方角の向き(北や上)を合わせる
- 色補正(赤色不足を補う等)、ノイズを減らす
- AIで「気になる場所」を見つけ、地図のように印(ホットスポット)を付ける
④ 体験画面(Web)で見せる
- 最初は YouTube 360 をページに埋め込むだけでOK
- 慣れてきたら Pannellum / A-Frame / WebXR に移行
- 評価:わかりやすさ・気分の悪さが出ないか等をチェック
1. 導入チェックリスト(現場での確認ポイント)
1-1. 撮影/収集
- 解像度:水中では細部が見えにくいので、できれば 5.7K 以上(理想は 8K/60fps)。
- 光量:水中は青っぽく暗くなりやすい。明るいライト+拡散板が有効。
- 距離の基準:レーザーの点や、既知サイズの物体を写し込み、後で大きさを推定できるようにする。
- ログ:方位(コンパス)、深さ、流れ等の記録があると判断の助けになる。
- 権利:YouTubeの動画を使う際は、規約やライセンスに注意。
1-2. つなぎ(ステッチ)
- 露出や白バランスを整え、つなぎ目(縫い目)が目立たないよう調整。
- 水中は模様が少なく、つなぎがズレやすい。手動微調整で対応。
- 仕上げは「横長の球面画像(2:1)」で出力しておくと後工程が楽。
1-3. 見やすく補正(方向・色)
- 上下や北の方向を統一(「いつ見ても向きが同じ」だと迷いにくい)。
- 赤色が弱くなりがちなので色補正(チャートがあればベター)。
- 暗所ノイズは動画フィルタで軽減(例:FFmpeg の
atadenoise)。
1-4. AIで注目点を自動抽出(必要に応じて)
- 球面の画像を6つの面(キューブマップ)に分けて通常のAI(YOLO等)にかける方法が扱いやすい。
- 見る方向の周辺だけを高精細にする「Tangent Image」という方法もある(軽くて速い)。
- 見つけた場所の座標(向き)を記録して、あとで画面に印(ホットスポット)を付ける。
1-5. 見せ方(Web)
- 段階1:YouTube 360をページに埋め込み、時間に合わせて説明テキストを切り替える。
- 段階2:Pannellum(または A-Frame)で自社ホスト。ホットスポットを自由に配置。
- 段階3:AIの結果をリアルタイム表示。学習ログ(どこを見たか等)も取る。
1-6. 体験の評価(UX)
- 理解度テストやチェックリストで「前よりわかるようになったか」を確認。
- 視線の動きや注目箇所をヒートマップにするのも有効。
- 酔いや不快感のアンケート(SSQ)で安全面もチェック。
- 「確実さ(自信度)」の表示を入れて、過信を防ぐ。
2. まずは簡単:YouTube 360 を埋め込んで説明を同期
次のサンプルは、YouTube の 360°動画( 例の海中動画)を ページに埋め込み、再生時間に合わせて「説明パネル」の内容を切り替えるだけのものです。 HTMLに貼り付ければ動きます(サイトにアップするだけでOK)。
<!-- ▼ 動画と説明のボックス -->
<div id="player"></div>
<div id="note" class="card">ここに海中構造の説明が出ます</div>
<!-- ▼ YouTube IFrame API -->
<script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>
<script>
let player;
// 時間ごとの説明(自由に増減できます)
const notes = [
{ start: 10, end: 25, text: "主柱A:基礎部に砂の堆積(目安 3cm)" },
{ start: 26, end: 40, text: "リブR3:軽い腐食(次回の潜行時に近接確認)" },
{ start: 41, end: 60, text: "ケーブル結束部:緩み疑い(流れが強い地点)" }
];
// API 読み込み後に呼ばれる関数(必須の名前)
function onYouTubeIframeAPIReady() {
player = new YT.Player("player", {
height: "450",
width: "800",
videoId: "G5il6L8ExBg",
playerVars: { playsinline: 1 },
events: { onReady: onReady }
});
}
function onReady() {
setInterval(() => {
const t = player.getCurrentTime();
const n = notes.find(n => t >= n.start && t <= n.end);
document.getElementById("note").textContent = n ? n.text : "—";
}, 300);
}
</script>
補足:YouTube 360 で「向き(どちらの方向を見ているか)」そのものを取得することは難しいです。
向きに合わせて印を出したい場合は、次の「Pannellum」という自前の表示方法に進みましょう。
向きに合わせて印を出したい場合は、次の「Pannellum」という自前の表示方法に進みましょう。
3. 次の段階:Pannellum で自社ホスト+印(ホットスポット)
Pannellum は、横長の球面画像(2:1)や対応動画をブラウザで表示する軽いツールです。 下のサンプルは静止画ですが、動画にも応用できます。球面上の場所(向き)に 情報の印(ホットスポット)を付けられます。
<!-- ▼ Pannellum の読み込み(CDN) -->
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pannellum/build/pannellum.css"
/>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pannellum/build/pannellum.js"></script>
<!-- ▼ 表示領域 -->
<div id="panorama" style="width: 100%; height: 520px;"></div>
<script>
// 画像:equirectangular(2:1)を指定
const viewer = pannellum.viewer("panorama", {
type: "equirectangular",
panorama: "seafloor_8k.jpg", // 自分の画像に差し替えてください
autoLoad: true,
pitch: 0,
yaw: 0,
hfov: 95,
hotSpots: [
{ pitch: -12, yaw: 55, type: "info", text: "主柱A:堆積" },
{ pitch: -3, yaw: 122, type: "info", text: "配線結束:緩み疑い" }
]
});
// あとから印を追加する関数(AIの結果などを反映できます)
function addHotspot(yaw, pitch, label) {
const id = "hs_" + Math.random().toString(36).slice(2);
viewer.addHotSpot({ pitch, yaw, type: "info", text: label, id });
}
</script>
3-1. 360°動画を扱う時の目安
- 形式:equirectangular の MP4(H.264/HEVC)。8K なら 60〜120 Mbps 程度を目安。
- サーバ設定:HTTP/2 以上、部分読み込み(Range リクエスト)対応。
- メタデータ(Spherical Video V2)を付けると再生互換性が上がります。
# 例:YouTube向けの球面メタ付与(spatialmedia ツール)
python spatialmedia -i input.mp4 output_injected.mp4
注意:船舶名・人物・取水記録など機微情報が映る場合は、アクセス制御(認証、署名URL、VPN、IP制限)を必ず設定してください。
4. AIで「気になる場所」を見つける(やさしい説明)
4-1. 基本の考え方
- 球面画像(ぐるっと全方向)を、6つの面(前後左右+上下)に分ける。
- 各面は「普通の画像」になるので、一般的な物体検出(YOLO 等)を使える。
- 見つかった位置を、球面上の向き(yaw/pitch)に戻して、印を打つ。
4-2. 位置を球面の向きに戻すイメージ(擬似コード)
# キューブ面内の座標(u, v) から 球面の向き(yaw, pitch) を計算する例
# ※あくまでイメージ(擬似コード)です。実装は環境に合わせてください。
import math
def vec_from_face_uv(u, v, face):
# u, v は各面の -1..1 の正規化座標(中心0)
if face == 'front':
x, y, z = u, v, 1
elif face == 'back':
x, y, z = -u, v, -1
elif face == 'right':
x, y, z = 1, v, -u
elif face == 'left':
x, y, z = -1, v, u
elif face == 'top':
x, y, z = u, 1, -v
elif face == 'bottom':
x, y, z = u, -1, v
# 正規化
n = (x*x + y*y + z*z) ** 0.5
return (x/n, y/n, z/n)
def vec_to_yaw_pitch(x, y, z):
yaw = math.degrees(math.atan2(x, z)) # -180..180(左右の向き)
pitch = math.degrees(math.asin(y)) # -90..90 (上下の向き)
return yaw, pitch
4-3. 水中ならではの下処理
- 色補正:赤みが弱い映像は、赤チャンネルを少し強めると見やすい。
- ノイズ:暗い場所のザラつきは動画フィルタで軽減(FFmpeg など)。
- 濁りや浮遊物:連続フレームで共通しているかを見て、一時的な点は無視する工夫が有効。
4-4. FFmpeg 例(配信向けに整える)
# ノイズ軽減+リサイズ+ストリーミング最適化の例
ffmpeg -i input_8k_er.mp4 \
-vf "hqdn3d=2:1:3:3,scale=7680:3840:flags=lanczos" \
-c:v libx264 -preset slow -tune film -profile:v high -level 5.2 \
-pix_fmt yuv420p -b:v 90M -movflags +faststart \
output_8k_stream.mp4
5. 台帳(メタ情報)の持ち方(最低限)
動画・画像の基本情報
- VideoID, タイトル, 撮影日時, 場所(任意), 水深, 流れ
- 形式(2:1 の球面画像/動画), 方角の基準(北、上)
印(ホットスポット)
- 時間(開始/終了)
- 向き(yaw/pitch), 視野(任意)
- 種別(構造/生物/異常/器材), ラベル, 自信度
- 参考リンク(写真・図面・PDFなど)
評価ログ
- どこを見たか(向きと時間)
- 理解度テストの結果
- 酔いや不快のアンケート(SSQ など)
6. 品質の目安と受け入れ条件
- 見え方:8K の球面映像で、主要な部位が拡大せずに判別できる。
- 向き:視点を変えても「北や上」の基準が崩れない。
- AI:誤判定が多くならないよう、疑わしい所は手動確認する運用に。
- 体験:理解が以前より良くなったか(テストで確認)。酔いが出ないか。
- 権利:肖像や機微な情報がある場合はアクセス制限をかける。
7. 90日ロードマップ(無理なく段階的に)
- 0–30日:YouTube 360 を埋め込んで時間同期の説明を付ける。簡単な理解度チェックを作る。
- 30–60日:Pannellum に移行。8K 再生とホットスポット配置。必要なら簡易AI(よく見る所の自動提案など)。
- 60–90日:AIの精度を改善。体験のABテスト(2パターン比較)で伝わりやすさを検証。
8. リスクと対策(現場で困らないために)
- 濁り・暗さ:できるだけ明るく、色を補正。撮影手順を定めて再現性を上げる。
- AIの間違い:「AIの推測にすぎない」ことを画面に示し、最終判断は人が行う。
- 酔い:ズームや回転のスピードを制限。固定視点モードも用意。
- 権利:限定公開やアクセス制御を必ず設定。外部配布は慎重に。
9. 最終チェックリスト(出す前に見る項目)
- 【素材】解像度・明るさ OK / 距離の目安(基準物)ある?
- 【処理】つなぎ目は目立たない? 向き(上・北)は整っている?
- 【補正】色・ノイズは許容範囲?
- 【印】重要箇所にホットスポットが付いている? 説明は伝わる?
- 【体験】理解度は改善? 酔いは出ない? フィードバックは取れている?
- 【配信】8K再生OK? 回線とサーバは耐えられる? アクセス制御は設定済?